| 12 世紀転換期を迎える福井県(2) | |
 ▲外国人の技術研修 外国人の技術研修もさかんに行われるように なった。たとえば県では、毎年、中国・浙江省 より研修生を受け入れ、県機関や民間企業で 研修を実施している。写真は林業実習のよう す。 福井県総合グリーンセンター提供 |
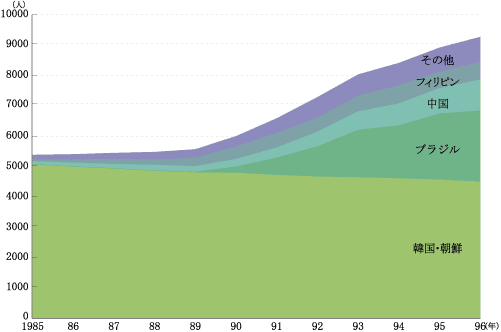 ▲福井県の外国人登録者数(1985〜96年、各年末現在) 労働力不足が顕著になった1980年代末から県内の外国人登録者数は急増した。とりわけ、90年 (平成2)6月の「出入国管理及び難民認定法」(入管法)改正により不熟練労働分野への外国人の 受入れ拒否が明確になると、就労範囲の制限のない「日本人の配偶者等」または「定住者」として の在留資格がある日系人労働者への求人が殺到し、県内でもブラジル、中国ー国籍の外国人登 録者数の伸びが著しくなった。『福井県統計書』による。 |
| 他方で、福井県をとりまく環境は、世紀転換期を迎えて大きく変容しつつあります。 なかでも顕著な変化は、「国際化」の進展にみられます。もともと福井県の主要産業である織物や特産品である眼鏡枠は輸出に力点をおいたグローバルな商品でしたが、80年代の、日本経済の国際的地位の上昇とともに、県内企業の海外進出や外国人労働者の県下への流入が進み、また県民の海外渡航や外国の人びととの交流の機会も飛躍的に増えました。しかし、同時に「国際化」は、産業の空洞化や米市場の開放といった負の影響を県内の主要産業にもたらしています。このため、多就労により経済的な安定をはかるという、県内の典型的な家族イメージもその転換を迫られており、少子・高齢化への抜本的な対策が避けられなくなっています。 さらに環境問題の深刻化、高度情報社会の進展など県民が直面する課題はますます複雑なものになってきました。このほど福井県では、88年の「新長期構想」の人口見通しを下方修正し、県民の参加システムの整備と効果的・効率的な行財政運営による地域づくりを強調した改訂を行いました。世界をみつめつつ地域社会の将来に思いをめぐらすという複眼的な思考をもって諸問題の解決に積極的に参加するという姿勢が、今後の県民にますます求められることになるでしょう。 |
|
県内企業の海外への事業展開は、1962年(昭和37)8月に酒伊繊維工業が東レ・三井物産と 提携してセイロンに設立したナイロン織物染色 合弁企業が最初で、その後60年代後半からア ジア、アメリカを中心に合弁企業の設立が進 む。85年のプラザ合意後の円高の進行にとも ない海外への展開を試みる企業が激増した が、近年の長期不況のなかで動きはやや停滞 している。『福井県企業の海外事業所調査』に よる。 |
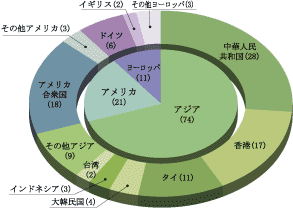 |
 福井市の化学メーカー日華化学は、東アジア・東南アジアなどで 積極的な海外事業を展開する企業の一例である。1988年にはアメ リカへ事業を拡大し、サウスカロライナ州にNICCA U.S.A.を設立した。 日華化学株式会社提供 |
|