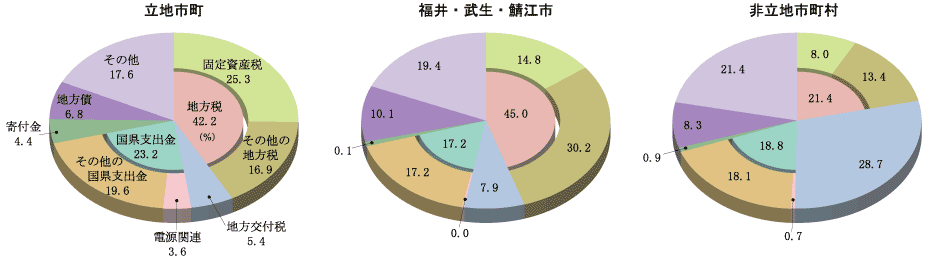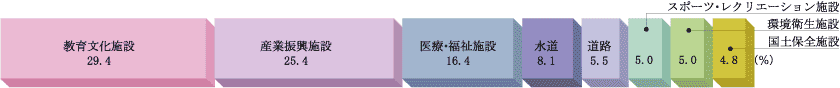| 11 原子力発電所の立地と地域振興(2) | |
| しかし、70年に最初の2基の原子炉が運転開始となった直後から事故や故障が相次ぎ、原電の安全性に対する県民の不安が急速に強まり、立地に対する住民の反対の声が高まりました。71年には立地を決定していた大飯町で町長リコール運動がおこり、新町長のもとで建設の一時凍結が行われ、また小浜市田烏への誘致の動きも地元漁民や労働団体などの反対により72年に市長が誘致断念を表明することになります。 県や立地自治体にとっても、原電の建設・運転・安全などの管理が国の一元的責任のもとにあり、国・企業からの一方的な連絡以外に情報が得られないという状況は、住民の安全管理のうえで重大な問題となりました。このため、71年8月には県・立地市町と施設設置者との間で最初の「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」が締結され、新増設計画に対する自治体の事前了解、異常時の即時通報、自治体の立入り調査権などが盛り込まれました。しかし、95年(平成7)12月の「もんじゅ」事故に典型的に見られるように、設置者による情報の秘匿や報告の遅れは、依然としてくり返されています。 一方原電の新増設を推進する国および電力業界は、安全管理の強化とともに、立地自治体および周辺自治体の協力の見返りとして財政的な支援措置を実施することになります。 まず、74年6月には、電気事業者に課税し、原電の建設期間中、立地および周辺自治体に交付金を交付する電源三法交付金制度がつくられました。また76年9月には福井県に全国初の核燃料税の徴収が認められます。79年のアメリカのスリーマイル島核燃料棒溶融事故を契機に財政支援措置はより強化され、81年から、立地地域の電気料金の割引などの電源三法交付金制度の拡充、核燃料税の税率引上げなどが実施されました。さらに、地域振興の名目で自治体などへ電気事業者より拠出される寄付金も多額となりました。 これらの財政支援により、自治体では道路・公共施設の建設を中心に各種地域振興事業への取組みが進みます。しかしこの結果、住民は、安全性への不安を抱きつつ、雇用・財政面での原電への依存度をますます高めていくことになったのです。 |
|
 1974年(昭和49)6月1日、関西電力 大飯発電所建設にともなう原電道路 の一部として、大飯町犬見・本郷間を 結ぶ青戸の大橋が完成し、舟運のみ に頼らざるをえなかった大島半島の 住民に、待望の陸路が誕生した。 |