| 5 奥越電源開発(2) | |
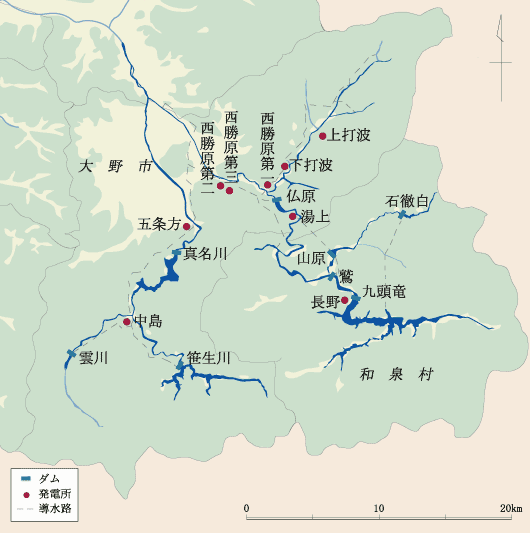 ▲奥越地域のダム・発電所 |
|
| つづいて、57年から九頭竜川本川の電源開発事業が北陸電力と電源開発の2社競願のかたちで始まります。県の政界や経済界は地元利益に期待して北陸電力による建設を働きかけましたが、水没地区住民らは建設規模や補償額に限界のある北陸電力よりも、世界銀行からの借款をも見込む電源開発の計画を支持したため、事業の実施は困難に追込まれました。61年には電力界4長老の裁定により両社共同工事と決まりますが、和泉村側は補償内容を不満とし、62年3月には補償交渉が打切りとなるほどでした。 結局、電源開発が補償交渉の前面に出て補償額の上乗せを考慮することで交渉は再開され、事業は総事業費約400億円を予定して65年に着工となります。長野ダム(九頭竜ダム)など5つのダムが建設され、68年には電源開発の長野・湯上両発電所、北陸電力の西勝原第3発電所により、最大32万2000キロワットの発電が開始されました。しかし、この時すでに、わが国の発電の主力は水力から火力へと移行しており、さらに時代は原子力発電の曙光をみていたのです。 |
|
 ▲現在の和泉村荷暮 ダム湖の出現によって孤立し、離村した和泉村荷暮では、 近年、雪のない春から秋にかけて、ふるさとにもどって過ご す高齢者が少なくない。離村のさいに家並みが解体された 集落には、家屋が再建され、1995年(平成7)には、電気が 通った。 |
 ▲真名川ダム ▲真名川ダム1965年(昭和40)9月の集中豪雨で壊滅的な被害をうけた大野郡西谷村は、 下流の真名川ダム建設により水没することになり、廃村を決議、70年6月、 大野市に編入された。 建設省近畿地方建設局九頭竜川ダム統合管理事務所提供 |