| 20 羽二重から人絹へ(1) | |
| 第1次世界大戦が終わると、1920年恐慌を契機として、絹織物輸出の凋落が始まりました。これに代わって登場したのが人造絹糸(人絹)織物です。人絹は、木材パルプなどのセルロースを溶解し、細孔から噴出して糸を作る人造繊維です。日本で人絹糸メーカーが勃興するのは大戦期になってからですが、その後20年たらずで日本は世界最大の人絹工業国になります。 |
 ▲福井人絹取引所(1933年) 福井人絹取引所は、大阪・東京との3者競願のなかで地元政界・実業界あげて の激しい陳情運動の結果、ようやく1932年(昭和7)4月1日、正式認可を得て設 立された。当初、39人の会員で発足し、西野藤助が初代理事長に就任した。 福井市立郷土歴史博物館蔵 |
| 人絹は当初フィラメント(長繊維)糸を主体に製造されたため、製織はおもに従来の輸出羽二重産地で行われました。福井県では、綿糸を経糸に用いる交織織物の製織をへて、昭和初年には緯糸・経糸ともに人絹を用いる双人絹織物の生産が本格化し、1928年(昭和3)末には県内の人絹糸の消費量が生糸のそれを凌ぐことになります。 羽二重が欧米の先進国市場へ輸出されたのに対し、人絹織物の輸出先は英領インド、蘭領インドなどのアジアをはじめ、オセアニア、アフリカといった後進国市場でした。31年末の金輸出再禁止後の円為替の下落と生産コストの低下を背景に、人絹織物はこれらの地域への輸出を急増させて、わが国の有力な外貨獲得産業の1つとなりました。 福井産地も人絹織物業の筆頭産地として急成長をとげ、県内の絹人絹織物の製造場数は、26年から36年までの10年間で3.3倍にもなります。織機を100台以上所有する工場も100有余となり、大野郡、今立郡などでは1000台前後の大工場も出現しました。嶺北の農村部では、子女のこうした工場への通勤や寄宿舎への入寮が増加し、さらに自家経営に乗り出す農家も増え、農業恐慌の打撃は機業からの現金収入の確保により緩和されたのです。 |
|
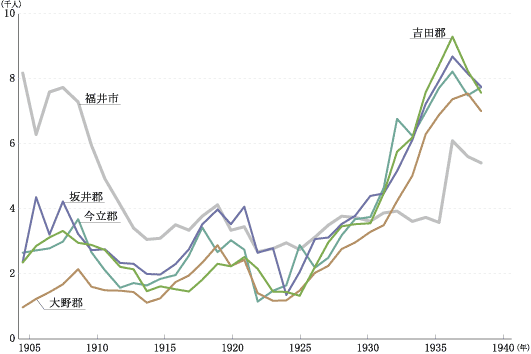 ▲絹・人絹織物の主要郡市別職工数(1905〜38年) 『福井県統計書』による。 |
|
 ▲坂井郡春江村の機業地帯と機業場(1933年) 春江村は明治中期以降、中小地主の投資に支えられて機業地帯として発展した。第1次大戦期には緯糸に撚糸を用いた縮緬を中心に生産 を伸ばし、人絹織物への転換後も縮緬に重点をおく産地であった。左の写真にある力織機は、右の列は台座と枠が木で作られた半木製力 織機であるが、左の列は新鋭の鉄製力織機である。ただし、県内力織機の大半は半木製で、1938年(昭和13)の時点でも鉄製の数は1割に も満たなかった。 福井県立図書館蔵 |
|