| 15 対岸貿易港・敦賀(1) | |
 ▲金ケ崎棧橋と「満州丸」(絵はがき) 満州丸(3054トン)は1933年(昭和8)5月に朝鮮北部航路に就いた。このほかにも「さいべりあ丸」(3462トン)、 「はるぴん丸」(5167トン)、「気比丸」(4522トン)らが大陸と敦賀を結んだ。 福井県立博物館蔵 |
|
| 1899年(明治32)7月、敦賀港は新潟・伏木・七尾港などとともに外国貿易港に指定されました。これは、90年にロシア皇帝がシベリア鉄道建設を発表して以来、将来のロシア貿易を見通した敦賀が開港の請願・建議をくり返した結果でした。 大和田荘七ら敦賀の商人は、翌年「敦賀外国貿易協会」「敦賀貿易汽船会社」を設立し、敦賀・牛荘(中国遼寧省)間の航路を開設して大豆・豆粕の直輸入を始めました。1902年2月には、敦賀・ウラジオストク(ロシア)間に日本海命令航路が開設され、さらに07年10月には、横浜・神戸・関門(下関・門司)とともに国費経営の第1種重要港湾に指定され、敦賀は日露戦後の大陸経営やウラジオストク、シベリア鉄道との連絡をも視野に入れた、国際貿易港として期待されたのです。 1914年(大正3)7月に第1次世界大戦が始まると、日本から物資の不足したヨーロッパやアジアに向け多くの商品が輸出され、積出し港である敦賀港もにぎわいました。また、国際貿易港にふさわしい港湾修築工事も明治・大正期と大正・昭和期の2度にわたって行われ、金ケ崎岸壁・蓬莱岸壁や主要な港の施設など、今日の港の原形ができあがりました。 ところが「ウラジオ景気」に湧いた敦賀港も、ロシア革命とその後のシベリア出兵で景気の急速な冷込みに見舞われます。敦賀は、不振の外国貿易から植民地圏貿易、とりわけ対朝鮮貿易へと活路を見い出そうとしました。18年4月に敦賀・清津間政府命令航路が開設され、朝鮮牛の移入もすすめられました。29年(昭和4)にはその数も6800頭を数えました。 さらに32年の「満州国」建設以後、朝鮮北部の清津・羅津・雄基は「満州」への新しい門戸として重要視され、これを機に、敦賀・新潟・伏木港など日本海側諸港は「日本海の湖水化」をスローガンにいっそうの発展をはかりました。しかし全国的にみると、わが国の産業は太平洋岸から瀬戸内にかけての工業地域に集中し、もはや大陸に近いというだけでは優位性を見い出せなくなっていたのです。日本海側の諸港は相対的にその地位を低下させ、「裏日本」化がすすみました。 |
|
 1920年(大正9)6月に 設立された福井県対岸 実業協会は、県内諸物 産のウラジオストク・朝 鮮など対岸各地への販 路拡大を目的とした官 民一帯の運動組織であ った。写真は、同協会 が発行した機関誌の 第1号。 小浜市立図書館蔵 |
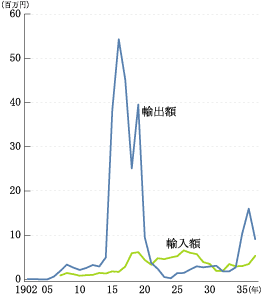 ▲敦賀港の貿易額(1902〜37年) |