| 9 鉄道の開通(2) | |
 ▲福井停車場の機関庫 JR東日本株式会社蔵 |
|
| ところで、官設鉄道計画に切りかわり、計画路線からはずされた三国町は、何度も路線の迂回を政府に願い出ましたが、計画は変更されませんでした。のち、1911年12月に金津からの支線が敷設されますが、かつての三国港の繁栄を取りもどすことはできませんでした。 一方、敦賀から舞鶴に向かう鉄道は、若狭3郡を中心とする熱心な敷設運動にもかかわらず、大正期まで実現しませんでした。18年(大正7)に敦賀・小浜間が開通し、東舞鶴までの全通は22年12月のことです。 また、1910年の「軽便鉄道法」を契機として、大正から昭和戦前にかけて多くの私設鉄道がつくられていきました。県内初の軽便鉄道は、武岡軽便鉄道の新武生・五分市間で14年1月のことです。その後県内各地での発電所建設がさかんになるにつれ、動力を電気に切りかえ、地方を結ぶ主要な交通手段として発展しました。 |
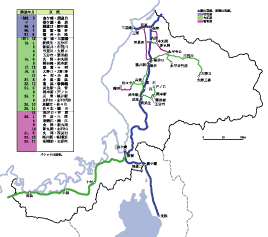 ▲戦前の県内鉄道路線図 太線は国鉄、細線は私鉄。 拡大図 55KB |
 (絵はがき) 昭和戦前の風景。駅前通りを西方向に 望む。軍服の男性や和服姿の女性でに ぎわう。 福井県立博物館蔵 |
|