| 2 地租改正(2) | |
| 1878年になると、石川県は「是ヲ受ケヌハ朝敵ナリ、然レハ外国え赤裸ニシテ追放ツ」と、政府の査定額を村むらに強要しました。それでも承服しない村が28か村残ったため、政府は翌79年2月、石川県令を更迭し、この28か村を除いて事業の終了を宣告しなければなりませんでした。 不承服の村むらには、近くの村と同様の税を実施するという処分が出されましたが、なおも抵抗を続けたため、9月にはその処分も取り消されました。このことは、すでに承服した村むらにも波及し、再審査を求める声は越前7郡に広がりました。こうして、12月には全国に例のない越前7郡の地租再調査を勝ちとることになりました。 翌80年9月、再調査の結果である石川県の見据額が発表されました。これは農民の期待を裏切るものでしたが、翌年に地価の修正を行うという妥協が成立し、石川県は81年1月、越前7郡の地租改正事業の終了を政府に報告しました。しかし、この直後に成立した福井県は、約束の地価修正を認めない方針をとったため、この後も地価修正の要求が続けられることになりました。福井県によって、越前7郡の地租改正事業の終結が政府に報告されたのは、83年7月のことでした。 |
 ▲測量器具 地租改正のときに使用したと伝えられ、 水平角・仰角が同時に計測できるように なっている。 清水町 斎藤三哲氏蔵 |
 ▲地籍図(坂井郡木部新保村字岡田屋敷) 地租改正作業により各村の字ごとに作成された地籍図は、条里制 などの古い土地利用のようすを記録している。この図は堀に囲まれ た中世の館の遺構を示している。 坂井町蔵 |
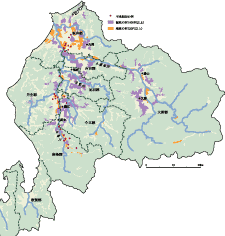 ▲ 増租の村と減租の村 不承服の28か村のように税額の増加した村むら は、大河川沿いのつねに水害・干害の危険にさら される地域であった。反対に減租の村むらは足羽、 今立郡の平野部のように、その多くが肥沃で生産 力の高い村であった。なお、現在の穀倉地帯であ る坂井平野の生産力が高まるのは、灌漑排水工 事の進んだ明治後期以降のことである。杉田定一 家文書による。 拡大図 64KB |