| 34 大野屋と大野丸(2) | ||
 ▲内山隆佐 大野市歴史民俗資料館蔵 |
 ▲内山七郎右衛門 『内山良休翁略伝』 大野市歴史民俗資料館蔵 |
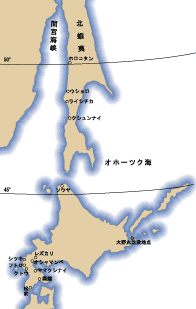 ▲大野藩蝦夷地探検概要図 拡大図 44KB |
| このような改革に大きな影響を与えたのは家臣の内山兄弟です。2人は「更始ノ令」以来、しだいに重要な役職につき、兄七郎右衛門(良休)はおもに銅山などの産物や財政を受け持ち、弟隆佐は大野藩西方領(丹生郡)の代官となり、その後「蝦夷地総督」になって活躍します。のちに2人とも家老になりますが、大野屋を設けこれを全国に広げたのは兄、大野丸に乗って各地をめぐり、蝦夷地調査の先頭に立ったのは弟隆佐です。 |
||
| まだ蝦夷地に入ることは容易ではありませんでしたが、寒さに慣れている大野人ならきっとやれる、開墾する場所を見つけ、新しい大野藩の領地を手に入れるのだという夢を追いました。56年(安政3)2月21日、約30人が最初に出発し、翌年も蝦夷に向かっています。58年、幕府は大野藩の努力を認め、北蝦夷のウショロに元会所を立て、そこに武士・百姓・漁民が一緒に住むとともに、ロシアなど外国を警戒するようにと告げてきました。2年後の60年(万延1)、北蝦夷地内の幕府が許可した土地は大野領と同じといわれ、藩では家臣一同、百姓・町人にまで酒を振る舞って祝いました。 しかし、大野藩の夢はここまででした。62年(文久2)藩主利忠が引退し、自慢の大野丸は64年(元治1)8月、根室で座礁し沈没するなど、不運に見舞われます。北蝦夷地の「開拓」も思わしくなく、ついに68年(明治1)3月29日、新政府へ許可地の返上願を出します。大野屋だけは着実に伸び、明治に入っても全国に店が広がっていったようです。 |
||
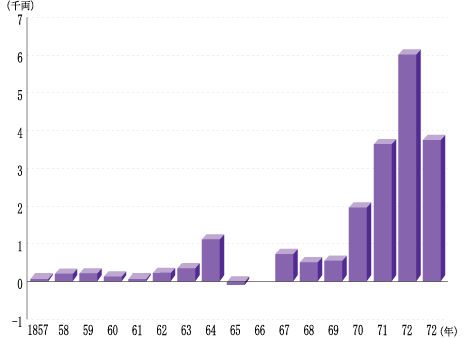 ▲箱館大野屋の利潤 1864年(元治1)は積立金利息487両、65年(慶応1)は損益63両、67年は積立 金91両・損益84両がふくまれる。66年は不明。明治期に入って利潤が大幅に 伸びたのが注目される。 |
 ▲大野丸帆船絵馬(大正期) 大野丸は、1858年(安政5)進水する。2本マストで長さ18間 (約32メ−トル)、幅4間の大きさ、マストの上に日の丸、船 尾には土井家の紋章がついている。藩士・農民など応募し た約30人が乗り組み、翌年からおもに敦賀・箱館間を往復 した。大野屋の商品を運送して利益をあげたという。59年8 月、大野丸は箱館の近海で難破したアメリカ商船ヘスペリ− ン号の乗組員を救助するといった活躍もしている。 大野市 柳廼社蔵 |
|