| 32 福井城下の町絵師・夢楽洞万司(2) | |
| 初代万司が唱える「夢楽」の号からは、この世の夢こそ楽とする、享楽主義的な主張が伝わってきます。この時期は、町人社会を中心に浮世の夢がもてはやされ、江戸で出版された黄表紙『金々先生栄花夢』(恋川春町)のように、中国故事「邯鄲夢の枕」に筋書きを借り、軽佻浮薄な風潮を茶化した戯作が流行しました。万司のいう「夢楽」も、こうした当世の流行にあやかった号であったと思われます。また、さらに洒落をきかして、煩悩を起こし俗世に墜落する「久米仙人」の説話に取材し、「夢楽」を叶える「万」の術を「司」る「仙人」を名乗ったのではないかと考えられるのです。 初代万司の絵馬は、安永期(1772〜80年)に増え始めます。絵柄には、伝統的な馬図のほかに、歌舞伎や浄瑠璃で演じられたさまざまな物語図がありました。その後、夢楽洞絵馬は旅の土産品として流行し、人びとの移動とともに普及します。さまざまな事情で村を離れた人びとが、帰郷のたびに個人・仲間で自村の堂社を飾っていったのです。北陸は真宗信仰の盛んな地です。旅ブームの到来は、京都の本願寺詣りの人気を高めたでしょう。夢楽洞絵馬が真宗信仰の習俗に支えられ、より広く受容されたことも考えられます。 夢楽洞は、越前で盛んな正月行事、天神講にまつる天神掛軸の製作も手がけていました。俗に「まんし天神」とよばれ、上半身を大きく描くところに特徴がありました。現在、この天神画は嶺北地方の鯖江以北に広がっています。教育の需要が高まり、各地に寺子屋が普及した幕末期に創始されたと思われ、画の筆致からも2代万司晩年の作と推定できます。学問・書の神とされる天神(菅原道真)をまつる習俗が武士から町人、農民へと広がるなか、夢楽洞の新商品、奇抜な大首絵の「まんし天神」が好評を博したのでしょう。 |
|
 ▲夢楽洞絵馬「紅葉狩り」 代々夢楽洞の絵師が得意とした画題で、県内に寛政から天保期(1772〜1844年)にかけての作品が数点残っている。 当絵馬は、夢楽洞初代・万司仙人の傑作のひとつ。12人の連名で、1790年(寛政2)に奉納された。画題は、能や歌舞 伎で知られる「紅葉狩」(平維茂の悪鬼退治の場面)。画中には「笄に角もばけてや 紅葉狩」の句がよまれている。 福井市江上 金劔神社蔵 |
|
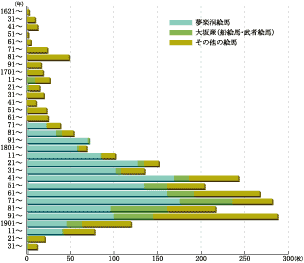 グラフは、越前(旧敦賀郡をのぞく)を対象とする福井県立博物館の絵馬調査の 成果(1996年 1月)による。調査した絵馬4000枚のうち、奉納年が判明するもの (一部推定を含む)の数を10年ごとに表した。19世紀の後半、江戸末期から明治 前期にかけて大きなピークが形成されることがわかる。とくに、明和末年(1771) の夢楽洞絵馬の出現以後、その数はいっきに増加し始める。 |