| 24 災害と飢饉(2) | |
| ■寛文の大地震と浦見川の開削 |  ▲現在の浦見川 浦見川水路を三方五湖めぐりの遊覧船が通っている。 三方町提供 |
| この地震による隆起のため、久々子湖に流れ込んでいた三方湖と水月湖の水が流れ出なくなり、周辺の村に水があふれ、田畑が水没した。あふれた水を久々子湖へ通すため、水月湖と久々子湖とを最短距離で結ぶ浦見坂を切り開いて、新しい水路(浦見川)を作ることになった。 小浜藩は、郡奉行をしていた行方久兵衛に工事を命じた。この工事は大変な難工事であったが、1664年(寛文4)に完成した。工事によって、水没した田畑がもと通りになっただけでなく、三方湖や水月湖の水位が下がり、その結果約400石(30ヘクタール)の新田が生まれることになった。 |
|
| おもな災害(風雨・旱ばつ・地震・大雪)29KB | 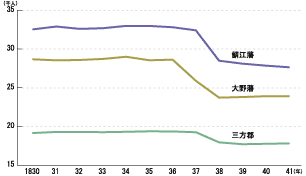 ▲鯖江藩領・大野藩領と小浜藩領三方郡の人口 天保の飢饉では全般的に人口の減少がみられるが、疫病の流行や 飢人救済の程度により個別的には減少しない村もみられる。 |
 墓の側面には、 「天保七丙申年飢饉翌丁酉とし疫病 流行人おほく死す無縁のものを此所 埋む因て追福のために建之 于時天保十四癸卯夏四月」 と刻まれている。 福井市西木田 |
|