| 19 藩財政とその窮乏(1) | |
| 藩財政のあり方は、家臣に領地を村むらで与えている場合と、領地は与えず藩の蔵からそれに相当する米を支給する俸禄制の場合とでは大きく異なります。前者の場合の藩の収入は、家臣に与えた領地を除いた大名の直轄領からの年貢が主たるものです。俸禄制の場合は、すべての領地からの年貢が収入となりますが、代わりに家臣への支給が大きな部分を占めることになります。 藩の収入は、百姓から取り立てられる米である物成(本年貢)、夫役の代わりに納められた夫米や雪垣代、山野河海の収益や産物などにかけられた小物成などからなっていますが、その中で最も大きな比重を占めたのは、いうまでもなく物成です。1675年(延宝3)の福井藩の場合、物成米の収入は全収入の87%、夫米は11%を占め、小物成はわずかに2%に過ぎませんでした。それに対し、北国と畿内とを結ぶ中継港敦賀・小浜をもった小浜藩の収入は、物成米の収入が全体の77%、米や荷物を運ぶ馬に課された駄別・沓代など流通への賦課をふくめると小物成は23%にものぼっており、この収入が福井藩に比して財政を豊かなものとしています。 俸禄制の小浜藩について17世紀なかばころの支出をみてみると、収入の35.3%が家臣への俸禄・扶持米、14.1%が国元と江戸の足軽・中間への扶持米、13.6%が隠居した前藩主への手当、6.1%が江戸での藩主家族などの賄いに費やされていますが、残りは国元と江戸での藩主の生活費や参勤交代の経費などにあてられました。 しかし、小浜藩をふくめ、各藩とも17世紀の後半には財政が行き詰まっていきました。これに対し、各藩では、家臣から知行の一部を借り上げる借知、商人からの借財、領民や商人への御用金の賦課、藩札の発行、専売制の実施などで対処しようとしました。 |
 |
| ▲小浜藩収支表 1800年(寛政12)から04年(文化4)までの小浜 藩の財政収入と支出の内訳を示したものであ る。上段には取米・家中渡米・払米・払米代金・ 小物成・江戸賄等・指引の項が設けられ、次の 段には1788年(天明8)あるいは94年から99年 までの平均の数値があげられ、それ以下の段 に各年の収支の仕切高が示されている。江戸 時代において、このような表化した財政史料は きわめて珍しいものである。 小浜市立図書館蔵 |
|
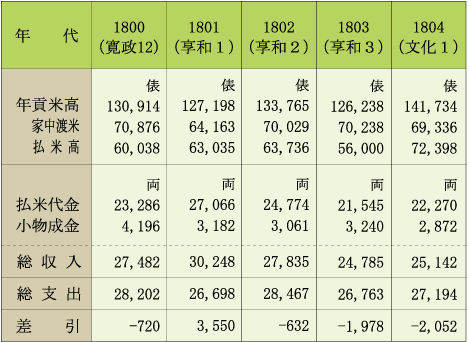 |
|
| ▲
小浜藩の財政収支(1800〜04年) |
|
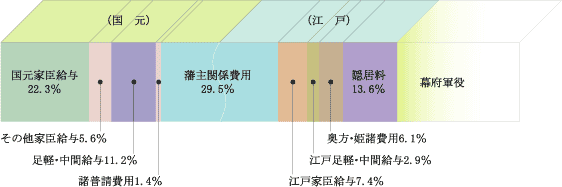 |
|
| ▲小浜藩初期の支出 1658年(万治1)ころの小浜藩の基本的な支出の構成費を示したものである。このころの小浜藩の収入は 約3万8000両前後である。支出は、大きく国元と江戸とに2分されるが、江戸における支出の多さがめだつ。 わずか1.4%の普請諸費用は城郭の修復があるときには一挙に膨れ上がり、また幕府から軍役が課せら れたときにはその支出もばく大なものとなる。 |
|