| 16 在郷町(2) | |
| 若狭の三方郡佐柿、大飯郡本郷・高浜は、戦国期には城下町でしたが、1669年(寛文9)に遠敷郡熊川とともに「泊り村」に指定され、宿場町としての機能ももつようになった在郷町です。佐柿は、東の椿峠をへて越前に通じる交通上の要地でした。本郷は丹後街道に沿い、上下村・市場村・下薗村の3か村からなっていました。高浜・小浜間の荷物運送の継場でもあり、町場には宿屋・茶屋などの店も開かれており、宝暦年間(1751〜63)からは野尻銅山の荒銅の積出港としても繁栄しました。高浜も丹後街道に沿う村で、1746年(延享3)の家数は603軒ですが、このうち浦方が175軒もあるのがほかの在郷町にはない特色です。 近世の城下町から在郷町に変貌したものに、吉田郡松岡・丹生郡吉江があります。松岡は、松岡藩の城下町として建設され、21年(享保6)の同藩の廃藩とともに、在郷町に変貌しました。福井藩による鋳物業や酒造業などの保護にもかかわらず、家数は停滞していました。吉江は、吉江藩の城下町でしたが、1674年(延宝2)に同藩が福井藩に併合され、諸役を免除されるなどの保護をうける在郷町となりました。 |
|
 ▲高浜町絵図 1854年(安政1)から56年ころの絵図である。縮尺は一様でなく、高浜 町の部分が周辺部に比べて拡大されている。戦国時代には若狭湾に 面した北方の山に城が築かれており、高浜は城下町であった。右端 に「京道」と記された道が本道で、この道の両側に町家が立ち並んで おり、西は丹後に通じていた。本道の北川に「舟大工丁」の町名がみ えるように、漁師町であった。 高浜町 荒木富造氏蔵 |
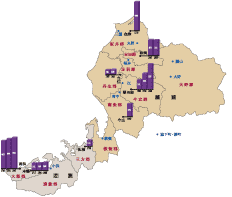 ▲おもな在郷町と家数 拡大図 33KB 越前・若狭のおもな在郷町の位置と家数を示した。 主要な城下町の間を埋めるように位置していたこ とがわかる。 |