また、両湊からは上方の荷物が北国へと送られました。この下り荷は、茶や木綿・繰綿や畿内で生産される手工業品でした。
荷揚げされた荷物は、問屋などにより取引されました。敦賀では、荷物を仲買に売渡す売問屋、仲買をつとめ売問屋から荷物を買い取り、小売に売り渡す買問屋があり、それぞれが取引にさいし得分をとりました。米と茶の取引では、売買の仲介をする仲が設けられ、仲銀を徴収しました。このほか、諸藩から委託されて年貢米の運送・売却にあたる蔵宿とよばれた商人もいました。
西廻海運の発達により敦賀や小浜湊は、やがて打撃を受けることになりました。北国から敦賀に運ばれていたぼう大な量の米は、しだいに大坂に直送されるようになり、天明期(1781〜89)には寛文期の3分の1に落ち込み、敦賀・小浜を中継地とする北国海運は衰退していきました。しかし、北国海運において北国から両湊までの往復は年に5、6回できるのに対して、西廻海運は北国と大坂を1往復するのが限度であり、海難の危険性もあるなど難点がありました。また、両湊には、ここから北国へ向かう下り荷が集まっており、湊の役割をもち続けました。
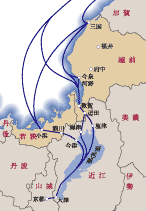
▲大津・京都への輸送経路
拡大図 24KB
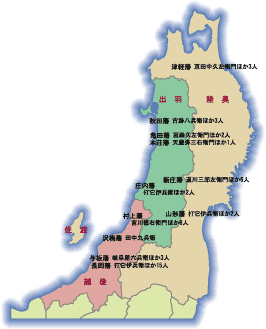
▲敦賀商人が蔵宿をつとめた
北国諸藩(1682年ころ)
「遠目鏡」によると、上記のほか福
井藩・大野藩・丸岡藩・大聖寺藩の
蔵宿をつとめた商人がいた。また、
丸岡藩・津軽藩は敦賀に蔵屋敷を
置いていた。 拡大図 42KB


「若狭敦賀之絵図」酒井家文庫 小浜市立図書館蔵
町の分布のほかに、御茶屋や代官屋敷・町奉行屋敷・塩蔵などの小浜藩の公的施設、津軽蔵屋敷などを見ることができる。
「敦賀町絵図」 京都大学総合博物館蔵
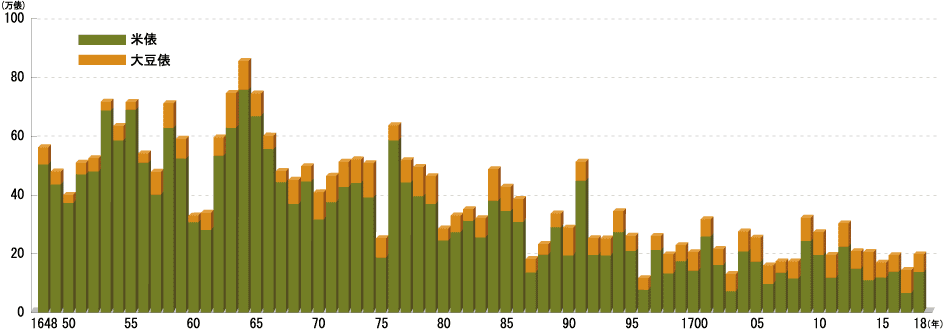
▲敦賀への米・大豆入津量(1648〜1718年)
「指掌録」より作成したもので、敦賀へもたらされたぼう大な米には諸藩の蔵米のほか、商人による商い米もふくまれていた。これらを運ぶ
ため敦賀へ入津した船数は、1664年(寛文4)には最も多く2670を数えた。