| 14 越前平泉寺(1) | |
| 鎌倉仏教が一定度の展開をみせた中世においても、天台・真言系のいわゆる旧仏教系の寺院勢力は強大な力をもち、政治的にも影響力をもっていました。白山を開いた泰澄が越前生まれであるという伝承を背景に、越前の大野郡平泉寺・坂井郡豊原寺・丹生郡越知山大谷寺が白山信仰の拠点として栄え、とりわけ平泉寺は10世紀以降、白山登拝の起点=越前馬場として強大な勢力を誇りました。 1182年(寿永1)から始まる寿永の乱(源平争乱)において平泉寺斎明(斉明)は、はじめ平氏軍を裏切りますが、のちに平氏軍に味方し、1183年の砺波山(小矢部市)の合戦で木曾義仲軍の前に敗北します。このとき平氏軍を破った木曾義仲は、『平家物語』によると戦勝祈願のため平泉寺に吉田郡藤島七郷を与えていますが、平泉寺に対する懐柔の意味もあったものと考えられます。 その後の平泉寺は、鎌倉幕府滅亡のさいには大野郡牛原荘地頭の北条氏一族淡河時治を攻撃して自害させ、南北朝の動乱のさいには斯波高経らの北朝方に属し吉田郡藤島で新田義貞と戦います。また戦国期には政治的に朝倉氏とほぼ同調し、一向一揆と対立しました。そして朝倉氏滅亡の翌年の1574年(天正2)、平泉寺は村岡山にたてこもっていた一揆勢に攻められ、諸堂・坊院は全て焼亡しました。 このように平泉寺は越前の政治の動向に大きな影響を与えましたが、その背景には平泉寺への初穂米である「平泉寺神物」をもとにした金融活動と、諸荘郷の代官職請負を通じて蓄積した経済力があったのです。また15世紀後半の平泉寺には、面打師として知られる三光坊、財蓮、1493年(明応2)に京都で神符と丸薬を売っていた杉本坊の栄祐などがおり、また16世紀中ごろには「日本一番ノ法師大名」と評され勢力を誇った波多野玉泉坊・飛鳥井宝光院など、さまざまな僧が居住していました。 |
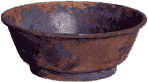 ▲銅製六器 六器は、密教法会のさいに用いる仏具の 一種。平泉寺南谷坊院跡からは、ほかに 陶磁製の調理具・食膳具・貯蔵具・茶道具 、各種石製品・木製品などが数多く発掘さ れており、僧侶たちの生活のようすがうか がわれる。 勝山市教育委員会蔵  ▲平泉寺南谷の道路・坊院跡 道路には河原石が敷きつめられ、側溝が設 けられている。道路の両側に残る多数の坊 院(僧侶の住居跡)跡の出入口はほぼ等間 隔に配され、計画性がみられる。 勝山市教育委員会提供 |
 越前馬場平泉寺から白山に至る「白山禅定道」が 描かれている。この図は「平泉寺境内図」(次ペー ジ)と対で屏風に仕立てられている。 勝山市 平泉寺白山神社蔵 |
|