| 11 絵図の語る荘園(3) | |
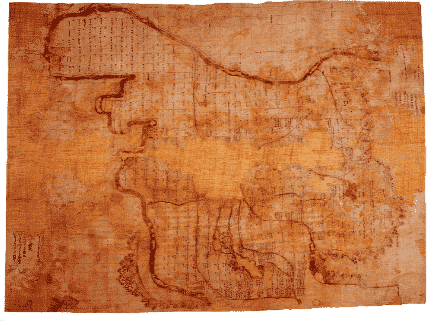 ▲(3)足羽郡道守村開田地図(天平神護2年10月21日) 道守荘は、占定された野地と寄進された墾田地をもとに東大寺による百姓などの墾田地 の改正(整理)、相替(交換)、買得(買収)によって発展した。しかし、県内の東大寺領荘 園は、律令国家の衰退と耕作を請け負う専属的農民の欠如により、10世紀には荒廃して いたことがわかっている。144×194cm 正倉院宝物 |
|
| ここでは、古代荘園図のなかで大きなものであり、豊富な文字情報に加え、景観描写も豊かな(3)足羽郡道守村開田地図についてくわしくみることにします。道守荘は、749年(天平勝宝1)の占定地とその後の足羽郡大領生江臣東人の寄進による墾田地100町とからなり、東大寺領荘園のなかでも最大規模のものです。その荘域は、北が「生江川」、西が「味間川」、東が「黒前川」「船越山」「寒江山」「木山」、南が「寺溝」に囲まれた地域に立地し、これらは足羽川(北)、日野川(西)、足羽山から兎越山の山並み(東)に相当し、福井市街地西南部の運動公園を中心とする社地区一帯の景観と一致し、この付近に比定されています。さらに、日野川の西に「難糟山」とあるのは清水町片粕集落西側の山塊に、荘園図の中央下部に「下味岡」「上味岡」とある小丘陵は運動公園造成のさいに削平された丘陵に相当する点などが所在地を比定するうえで重要な根拠になっています。 | 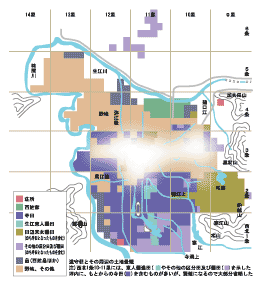 ▲足羽郡道守村開田地図の概要 拡大図 60KB |
 |
福井市街地西南部の景観。道守荘比定地の中央 あたりが、現在運動公園となっている。 建設省国土地理院提供 |