| 10 文書の語る荘園(2) | |
| 耕地の耕作にあっては、近隣の農民などに1年契約で土地を貸し与え、耕作前の春先あるいは収穫後の秋に借用料を支払わせる「賃租」(ちんそ)という土地の貸借形態がとられていました。この「賃租」による貸与料が荘園経営のおもな収入であったようです。支出としては「荘所」の建物や垣の新造・移築・修理のための費用のほか、新たな田の開墾やそれにかかわる溝の開削・修復のための費用などです。その支出費用に占めるおもなものは、労働に対して支払われた食料と賃金で、このような労働力は雇傭労働の形態でまかなわれていたようです。 この桑原荘をはじめとする荘民を持たない古代の荘園経営にとっては、「賃租」 農民のような請負耕作者や雇傭労働者を確保することが、荘園の興廃にかかわる重要な課題であったと考えられます。したがって、越前国の東大寺領荘園、たとえば桑原荘や道守(ちもり)荘・鯖田国富(さばたくにとみ)荘などの成立や経営に、在地の有力者である生江臣東人や品遅部君広耳などが深く関与しているのは、労働力の調達や編成を円滑にし、より安定した荘園経営を進めるために必要であったからだともいえるでしょう。 |
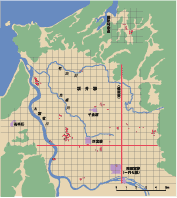 ▲東大寺領荘園と品遅部君広耳寄進墾田の分布 東大寺越前国鯖田国富荘は、坂井郡大領の品 遅部広耳の寄進によって成立する。広耳が寄進 した100町の田は、当初は坂井郡に散在していた が(図中の●)、やがて、荘園をできるだけ1つの領 域にまとめる(一円化)ように東大寺が動き出し、九 頭竜川近くの領域にまとめられた。東大寺越前国 桑原荘の正確な位置は不明。 拡大図 41KB |
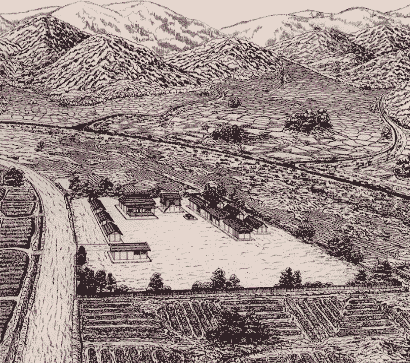 ▲桑原荘の景観 桑原荘の荘所(経営拠点)は、金津町桑原の竹田川自然堤防上にあったと考えられ る。「桑原庄券」から、垣のなかに草葺や板葺の家屋や倉庫があったことがわかって いる。近県で発掘された荘園遺跡からみて、これらの建物がコの字形に配置されると 考えて復元したもの。宮本長二郎氏指導。 『福井県立博物館常設展示図録』より転載 |
 ▲桑原荘比定地 金津町桑原 |