| 8 土地に残された古代(2) | ||
 ▲古代の青郷の比定地 高浜町中心部以西。中央の山は青葉山。 高浜町提供 |
||
| そこで、現在の地名を手がかりとして青郷下の故地を求めれば、「青里」は高浜町青、「小野里」は高浜町神野・神野浦、「川辺里」は京都府舞鶴市の河辺川沿いにある河辺由里・河辺原・河辺中、さらに「氷曳」は高浜町日引、「田結」は舞鶴市田井の付近にそれぞれ比定することができます。したがって、青郷の広がりは福井県の高浜町から京都府舞鶴市にまたがる広範な地域であったことがわかります。この青郷の例だけに限らず、とくに若狭国の古代地名のなかには、そのままの表記で、あるいは漢字を変えながら、現在まで存続しているものがかなり多くみられます。たとえば、上中町玉置・三宅、小浜市遠敷、大飯町岡田、三方町三方などは古代の郷(里)の名そのままですし、大飯町佐分利川、高浜町上車持・下車持、三方町能登野などは、それぞ佐文(分)、車持、能登という郷(里)名にちなむものです。 圃場整備以前の福井平野には、写真のような碁盤目状の土地区画がいたるところにみられました。このような一辺約109メートルを基本とした規則的な正方形の地割形態を条里地割といいます。この正方形の区画は、奈良時代には「坊」、平安時代ごろからは「坪」とよばれるようになり、その面積が古代の一町です。条里制は、土地の所在地を数詞で何条何里何坊(坪)と表現し、合理的な土地表示様式の基礎単位として機能していました。班田収授の実施にあたっても、それは有効であったと考えられます。この条里地割が、つい最近まで深く土地に刻まれながら、連綿と受け継がれてきていたわけですから、古代の地割形態が後世への遺産として確実に生き続けていたことになります。 古代から現代へと悠久の時の流れをこえ、古代の息吹を土地に残しながら、地名は今も生き続け、条里地割は姿を消してしまいました。 |
 ▲若狭国遠敷郡青郷の関連地 田井浦は中世に丹後国志楽荘に押領されており、 田井が丹後国に編入された契機となった。河辺付 近も同じような経緯をたどったのであろうか。図は 国土地理院発行の20万分の1の地図に青郷関連 地を示したもの。 拡大図 115KB |
|
 ▲今も残る青郷 JR小浜線青郷駅構内 |
||
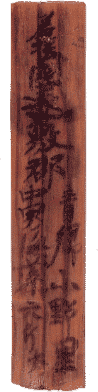 男作物木簡 海藻はワカメである 。小野の地名がみえ る。17〜20歳の男子 が中央政府に必要 な物資を税として運 んださいの荷札で ある。 平城京二条 大路跡出土 |
 ▲青郷からの贄木簡 鯛鮓(たいずし)や氷曳の地名がみえる。 平城京二条大路跡出土 |
 ▲青郷からの贄(にえ)木簡 きたい(干物のこと)を田結 から貢進した。天皇に進上 する食品を都にまで運んだ さいの荷札である。 平城京二条大路跡出土 (木簡は奈良国立文化財研究所蔵) |