
▲円覚寺の船絵馬
青森県深浦の円覚寺に伝えられたもので、中世末から日本海で活躍
した北国船の姿を伝える唯一の船絵馬である。1633年(寛永10)に敦
賀の商人庄司大郎左衛門が奉納したもの。
青森県深浦町 円覚寺蔵
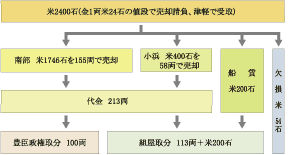
▲米売却をめぐる豊臣政権と小浜の豪商組屋の取分
豊臣政権は遠隔地での米の売却をするために、ばく大な
利益を豪商組屋に保証した。

▲ルソン壺
16世紀後半、フィリピン(ルソン)をへ
て輸入された中国広東省産の壺で、
葉茶の貯蔵用として珍重された。
滋賀県 彦根城博物館蔵
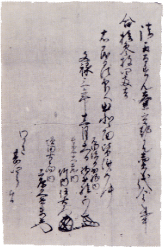
▲ルソン壺売代金請取状
豊臣政権の五奉行であるの石田
三成・長束正家・増田長盛の下代
が、豊臣政権から「るすん壷」の京
都での売却を委託された小浜の豪
商組屋甚四郎に、その代金の皆済
されたことを証したもの。
『越前若狭古文書選』
中世末以来小浜の商業を統轄してきた組屋は、豊臣政権の米を津軽で受け取り、その販売と運送とを行い、秀吉の朝鮮出兵にさいしてはほかの小浜商人とともに兵粮米を朝鮮への前進基地であった肥前名護屋に運送し、さらに加賀藩の蔵宿を務めるなどしたほか、当時珍重されていたルソン壺の購入・売却を豊臣氏の奉行衆からの依頼で行っています。