| 18 源平合戦と北陸道(2) | |
| この勝利に乗じた義仲軍は進撃を続け、7月28日に入京します。このころ、義仲は白山宮加賀馬場の本宮や金劔宮、平泉寺・気比社に社領を寄進し、それらの神人・衆徒を味方につけようとしています。また越前国府では、比叡山に牒状を送って圧力をかけ、味方につけことに成功します。しかし結局、義仲は天下を取ることはできず、後白河法皇を幽閉するというクーデターをおこし、翌年1月に、源頼朝の派遣した弟の範頼・義経軍に近江粟津で敗れ戦死しました。 兄頼朝の先兵となって活躍した義経ですが、彼も越前を通過しました。それは兄と不和となり、奥州平泉の藤原秀衡を頼って落ちのびていく途中でした。1186年(文治2)2月京をはなれた義経・弁慶らの一行は、逢坂関を越え大津の浦に出て、船で海津に着き、雪の中を荒乳(愛発)山を越え敦賀に至ったのです。しかし、出羽への船を見つけられず、木ノ芽峠を通って国府に入ったのち、平泉寺に立ち寄り、金津をへて加賀に入り、安宅関へと向かいました。 越前はめまぐるしく変わる勝者・敗者の姿を見続けたのでした。 |
 ▲白山神社境内 白山信仰の拠点である越前馬場として栄えた平泉寺は、神仏分離令により、 明治初年に白山神社と改めた。 |
 ▲平泉寺の僧兵たち 平泉寺長吏斎明にみるように、源平合戦のなかで平泉寺(白山 中宮)の神人・衆徒たちは、平泉寺の勢力を保全、拡大すべく源 氏・平氏方への去就を繰り返した。 「遊行上人縁起絵」 京都市 金蓮寺蔵 |
|
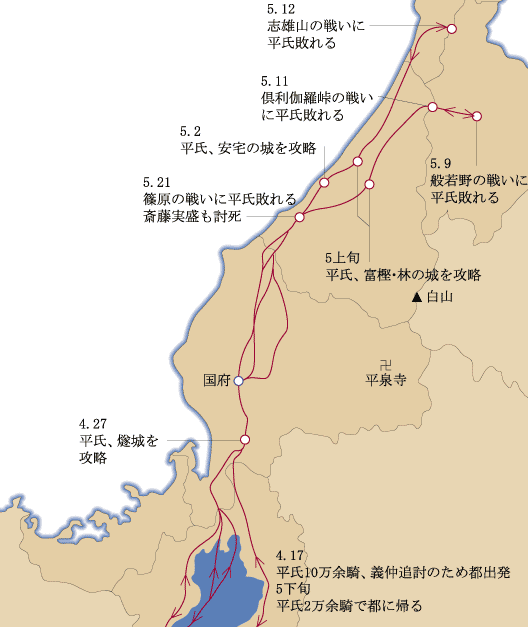 (1183年) 平氏が都を出発するさい、西日本や 東山道の近江・美濃・飛騨の武士は 参集したものの、東海道は近江より 東、北陸道は若狭より北の武士は参 集しなかった。 『平家物語』『源平盛衰記』より |
|